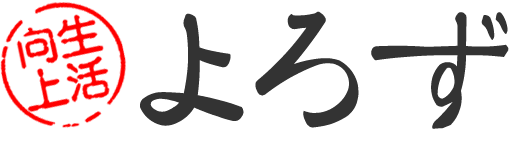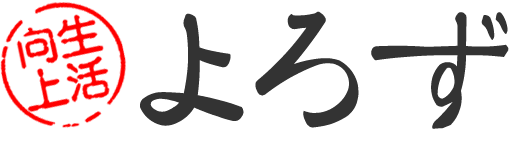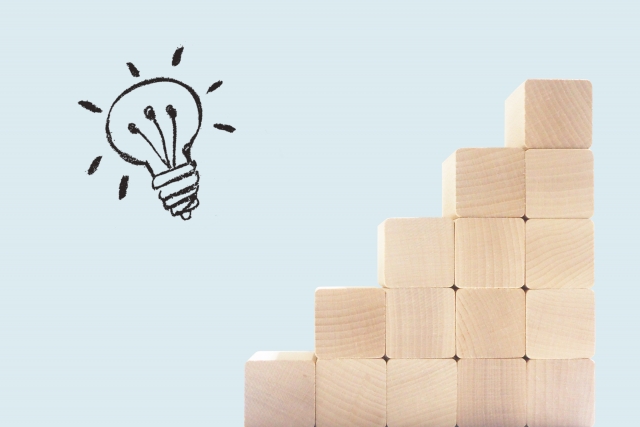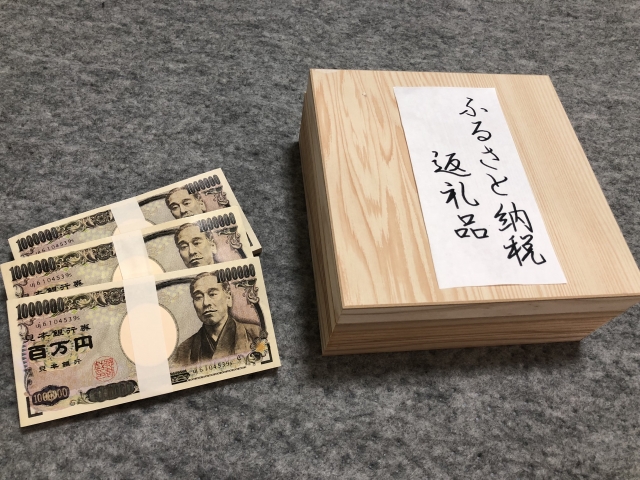金融の豆知識
相続法が40年ぶりに改正!知っておくべきポイント4つを解説相続法が約40年ぶりに改正

相続に関するトラブルは、どの時代でも必ず起こっています。特に近年は、家族形態の多様化や超高齢化といった背景もあり、相続に関する悩みやトラブルが増えてきていると言われます。
中でも、トラブルが多いと言われるのが、「相続対象の財産が不動産のみで分割が困難」、「遺言書がない」といった内容です。
トラブルが多い相続問題ですが、リスクを抑えるために何らかの対策をとっている人は少ないようです。
少し古いデータですが、2012年5月に一般社団法人・信託協会に実施された調査によると、生前に「相続対策を実施しなかった人」は全体の約8割にのぼっていたことがわかっています。
生前贈与や相続税節税といった具体的な対策をしていた人は、2割にとどまっている結果です。
(参考:「相続に関する意識調査」)
さて、相続に関するトラブルや不安が顕在化している中、平成30年7月6日に相続法が改正されました。
相続法が大きく改正されるのは、昭和55年(1980年)以来、約40年ぶりのことです。
法律の専門家だけでなく、日本人すべての人に関わる改正なので、最低限の知識は持っておく必要があります。
改正された相続法について、ポイントをご紹介します。
相続法はどこが変わったのか? ポイント4つ

○配偶者居住権の新設
配偶者居住権とは、被相続人が所有主である建物に配偶者が住んでいた場合、その建物にそのまま住み続けられるという権利です。
従来から住むこと自体は可能でしたが、配偶者はその権利を得る代わりに、預貯金などの他の財産を子どもなど配偶者以外の相続人に分配させることになっており、「家はあるけど生活費がない」というトラブルが起こっていました。
今回の改正では、建物の所有権の一部を子どもなど他の配偶者に相続させる代わりに、預貯金などの他の財産も多く得られることになりました。
つまり配偶者は、住み続けられる上に今後の生活費となる預貯金もしっかり相続できることになったのです。
○遺産分割前に預貯金を引き出せる
従来は、遺産分割が終わらなければ、配偶者などの相続人は金融機関から被相続人の預貯金を引き出すことができませんでした。
配偶者に、「葬式や生活費にかかるお金の工面が苦しい」といったトラブルが起こっていたのです。
そこで今回の改正によって、以下のようなルールができました。
・預貯金の一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払いを受けられるようにする。
・預貯金に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。
(参考:法務省パンフレット「預貯金の払い戻し制度の創設」)
つまり、引き出せる額や条件に一定の範囲はあるものの、従来よりも自由に預貯金を引き出せるようになったということです。
○財産目録がPCで作成可能
財産目録とは、自分の所有している財産を記録した一覧表のことです。
法的な拘束力がなく書式に明確な指定がないため、箇条書きのような簡易な書き方でも問題ありません。
この財産目録が、従来は手書き指定でしたが、改正によってパソコンで作成が認められることになりました。
○自筆証書遺言書が保管可能
自筆証書による遺言書は従来は、自宅や弁護士に預かってもらうのが一般的でした。
しかし、自宅の場合、紛失や改ざんの恐れもありトラブルのリスクが考えられます。そこで今回の改正では、法務局で保管できるようになり、より安全に保管できるようになったのです。
保管所の指定や管轄については、施工日である2020年7月10日までに定められることになっています。
相続法の施行はいつから?

法務省によると、相続法は2019年1月13日から段階的に施行されることになっています。
「自筆証書遺言の方式を緩和する方策」は2019年1月13日から、「預貯金の払い戻し制度」、「遺留分制度の見直し」等は2019年7月1日から、「配偶者居住権の新設」等は2020年4月1日から、施行される予定です。遺言書を法務局が保管してくれる制度である「遺言書保管法」の施行は、2020年7月10日からです。
(参考:法務省ポスター)
このように制度によっては1年以上のバラつきがあるので、「2019年1月からはまったく新しい制度だ!」と勘違いしないよう注意しましょう。
相続に関してもっと詳しく知りたい人へ
冒頭で「相続に関する悩みやトラブルが増加している」と言いましたが、この記事を読んでいる人は、相続について悩んでいたり興味を持っていたりする人でしょう。
ただ法律の知識は、読むだけで完ぺきに理解するのは難しいものです。
そこで、相続について簡単に詳しく知りたい人にオススメなのが、弁護士・司法書士の無料相談を利用する方法です。
相続法そのものについての知識はもちろん、自分の状況から、「今後どのようなトラブルが起こり得るか」、「どうすればスムーズに相続問題を解決できるか」と言った具体的なアドバイスをもらえるはずです。
(ライター:尾崎 海)
最終更新日 2019年03月22日 30323view この記事は作成から1年以上経過しています。情報が古い場合がありますのでご注意ください。
関連エントリー 融資審査に落ちる人に共通する4つのポイント
銀行や消費者金融から融資を受けるときに必ずあるのが、@s1@審査@/s1@です。審査がある... なぜ「つみたてNISA」は老後資金の備えとして注目されているのか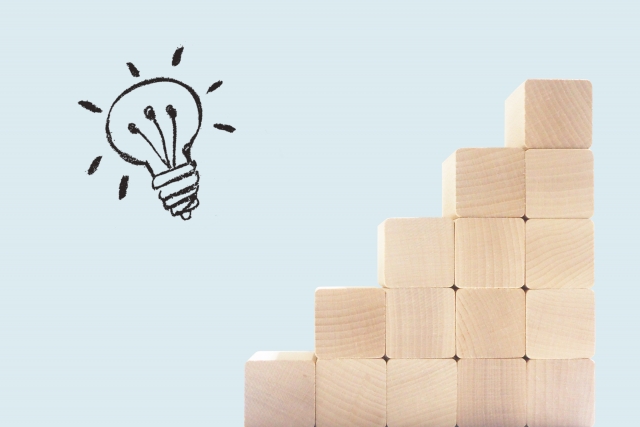
昨今、『老後資金は2000万円必要』などと言われています。
我々はどのようにして老後に備... 借金は早く返そう!放っておくととんでもないことに… 借金は放っておくとどんどん増える仕組みになっています。
高い利子と、複利と言って利子に利子が... ふるさと納税ってどんな制度?申請の流れや注意点を解説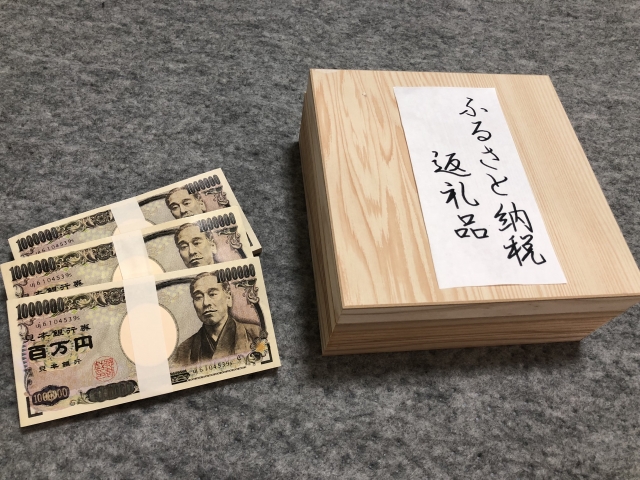
@b@「『ふるさと納税』という言葉は知っているけど、やったことはない。」
「興味はあるけ... 中古マンション購入の落とし穴!必ずチェックすべき場所とは?
マンション購入は中古であれ新築であれ、一生に一度の買い物となる場合がほとんどです。
購入... |